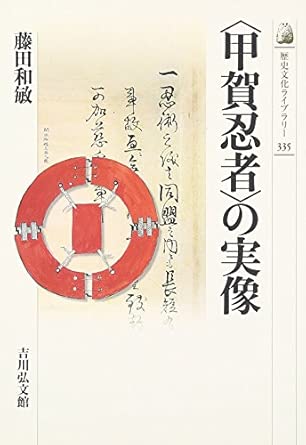昔から、忍者に興味があった。
著者の藤田氏は、じっさいに滋賀県甲賀郡甲西町役場に、3年間勤務したとのこと。
藤田氏が上げている資料のなかで特に興味深いのは、享保6年(1711年)に作成されたという、「甲賀衆 肥前切支丹一揆 軍役由緒書案」である。
これは、1673年に発生した島原キリシタン一揆に際しての、甲賀古士たちの従軍記録である。
敵陣に侵入して、敵の兵糧13俵を奪い、とかいろいろ功績が書かれてある。
由緒を語ることの意味
江戸時代は、甲賀古士のように幕府や個々の領主に対して由緒を主張することで自らの権益を権益を守ろうとした個人や集団が全国各地に出現した。
自分の祖先と家康とのつながりを主張した甲賀古士に対して、幕府は相応の処遇を考えた。
その事実から、彼らの由緒が現実の世界を生き抜くための方法として、機能していたことを指摘できるのである。
57ページ
伊賀越え: 光秀はなぜ家康を討ち漏らしたのか 2024/4/23小林 正信 (著)淡交社「天海・光秀同一説」大いにあり得ると思ってる……家康は光秀に恩義を感じて、いわゆる明智人脈をチョー優遇したんではないの??
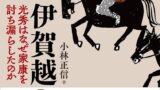
家康の従者二百名も犠牲となって(しんがりの、おとりの役目を引き受けて)、家康本体に、木津川を渡らせたのがすべての勝因らしい。
その差、4時間。
明智勢も家康探しに、血眼だったということがよくわかった。
だから、言うまでもなく、徳川家康と明智光秀は仇敵である。
この件、「伊賀越え」だけ見ればそうなる。
↑これは甲賀者ではなく、伊賀者にまつわる逸話だが、
徳川家康の「伊賀越え」、俗に言う「神君、伊賀越え」というのは、本能寺の変直後、忍者に先導されて、明智光秀から命からがら逃げることに成功したことである。
家康の従者二百名も犠牲となって…
この中に、どれだけ伊賀忍者がいたかはわからないが、歴史のすきまで彼らが多大な貢献? をしていたことは明らかであろう。
伊賀・甲賀の単郭方形城郭。
これは凄い!!!
弥生時代の環濠がここまで進化したというべきか。
類書に当たってはみたが、私はこういう独特の城郭群を生み出した、その発祥に興味があるのだが…
どれもこれも類書に発祥に関する記載はない。
林立する方形単郭の城郭群
https://www.keibun.co.jp/saveimg/kakehashi/0000000201/pdf_sub_3561_20161222143108.pdf
なかでも甲賀郡では、300もの城館が築かれています。なぜ、甲賀郡にこれほどの城館が築かれたのでしょう。
まさに、甲賀郡のような一村一城のような形態の小規模の村であっても、ひとつでも無視して中へ攻め入った場合、背後から攻められる可能があるため、どうしても、ひとつづつ落とさなければならないわけです。
4年前、現地へ行ってみた。
甲賀郡では、300もの城館が築かれています、とのことだが、小さな城というより館と言ってもいいもので、ここで白状すると、私には現地へ行っては見たが、こんもりと小高い丘みたいなものが確認できたが、それがかつて城という構造物だったのかどうかは確認できなかった。案内者がいなければダメだと思う。
実にためになるサイト ↓
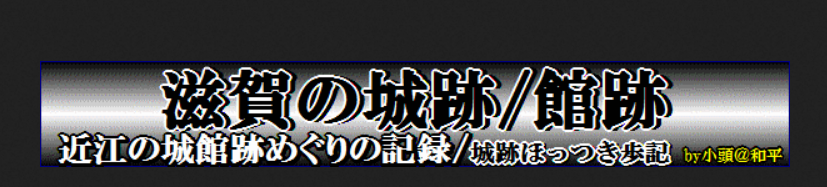

忍びの者 その正体 ; 忍者の民俗を追って 2021/ 筒井功 (著) 河出書房新社 忍者の実態のリアリズム。実像を追う。
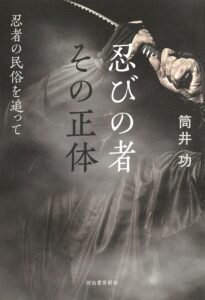
北条配下の風魔一党、猿引・植田次兵衞、伊賀・甲賀の単郭方形城郭から、伊達氏の黒脛巾組と会津・摺上原の合戦。コラム、図版多数の実証研究。
著者について
筒井功(つつい・いさお)
1944年生まれ。民俗研究家。 著書に『サンカの真実 三角寛の虚構』『葬儀の民俗学』『新・忘れられた日本人』『サンカの起源』『猿まわし 被差別の民俗学』など。
高知県幡多郡黒潮町加持(かもち)字猿飼ーー
土佐一条氏が居城を構えていた中村の市街から北東へ10キロほどに、加持という村があるという。
加持は「万葉集古義」などで知られる幕末の国学者・鹿持雅澄の名字の地で、雅澄は土佐一条氏の重臣であった。
応仁の乱のとき、前関白・一条教房に従い京都から土佐に下向してきたといわれる。
加持は加持川沿いの本村、田村、小川の3地区に大別されるがそのどれからも1.5キロばかり離れた北東部の山すそにささやかな集落があり、そこが猿飼だと。
猿回しの民俗を調べていた著者はそこで驚くべき見聞を得る。
長宗我部が台頭する戦国の土佐。土佐一条氏に使えた入江左近という人物がいた。
一条兼定公は当時、現宇和島沖の戸島という島に潜伏していた。
その一条兼定公の首を切ったのが入江左近の家来の猿回しの植田治兵衛だというのだ。
この事実を著者は、ルイスフロイスの「日本史」、残っている資料から実証している。
この話、あまりにも凄いと感じたがアマゾンレビューにも書き込みがなく、寂しく感じた次第。
忍者の系譜 (歴史散歩シリーズ) 漂泊流民滅亡の叙事詩 杜山悠 創元社 昭和47年
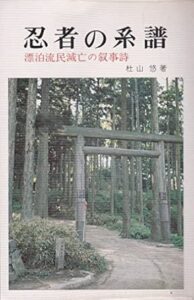
古い本だが私が読んだなかで最も印象に残る一冊。
とりわけ、類書になくて本書にある視点…
それは差別ー被差別の視点がある点である。
柳生の里も、じっさいに15年前ぐらいに1度だけ行ったが、あんな人里離れた場所が発祥とは!
柳生一族は、忍者ではないが、徳川時代が長かったせいか、よく整備された日本家屋、日本庭園などが各所にあり、とてもここが被差別の現場になったところだとは思えない。
ただ、柳生流の武芸なるものが、周辺住民との軋轢から出来上がったであろうことは確信する。
柳生家の発祥地は大和国添上郡柳生郷(現在の奈良市柳生地区)で、大和国北部にある。
また「楊生」・「夜岐布」・「夜支布」・「養父」とも記され、いずれも「やぎふ(やぎう)」と訓むという。
印地(いんじ)は、日本で石を投擲することによって対象を殺傷する戦闘技術、行為、行事である。
手で投げることを始めとして、投石器を使用するもの、日本手ぬぐいや畚(もっこ)をもってそれに代用するもの、女性が領巾(ひれ)を使用するもの、砲丸投げのように重量のある物を投げつけるもの、など様々な形態があった。
また投石技術でこの技術に熟達した者を、印地打ち(印地撃ち)、印地使い(印地遣い)等とも呼んだ。
印地の使い手を印地と呼んだり、技術や行為を印地打ちと呼ぶこともある。印字、因地、伊牟地とも書かれる。
文献上、「印地」の語が表れるのは、『平家物語』巻八の「向かえ飛礫、印地」であるが、「飛礫(つぶて)」の語の方が古く、10世紀後半成立の『宇津保物語』内の「かかる飛礫どもして方々にぞ、打たせ給へる」がある。
諸説あるものの、印地の語源については、「石打ち」の略とされる。
全国日本部落史料 菊池山哉著 1981/八切 止夫 日本シェル出版 八切止夫という作家を知っていますか?
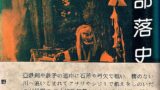
家康の正妻 築山殿: 悲劇の生涯をたどる (平凡社新書 1014) 2022/黒田 基樹 (著) 平凡社 著者が幻の奇書『史疑・徳川家康事蹟』をどう思っているのかに興味が湧く