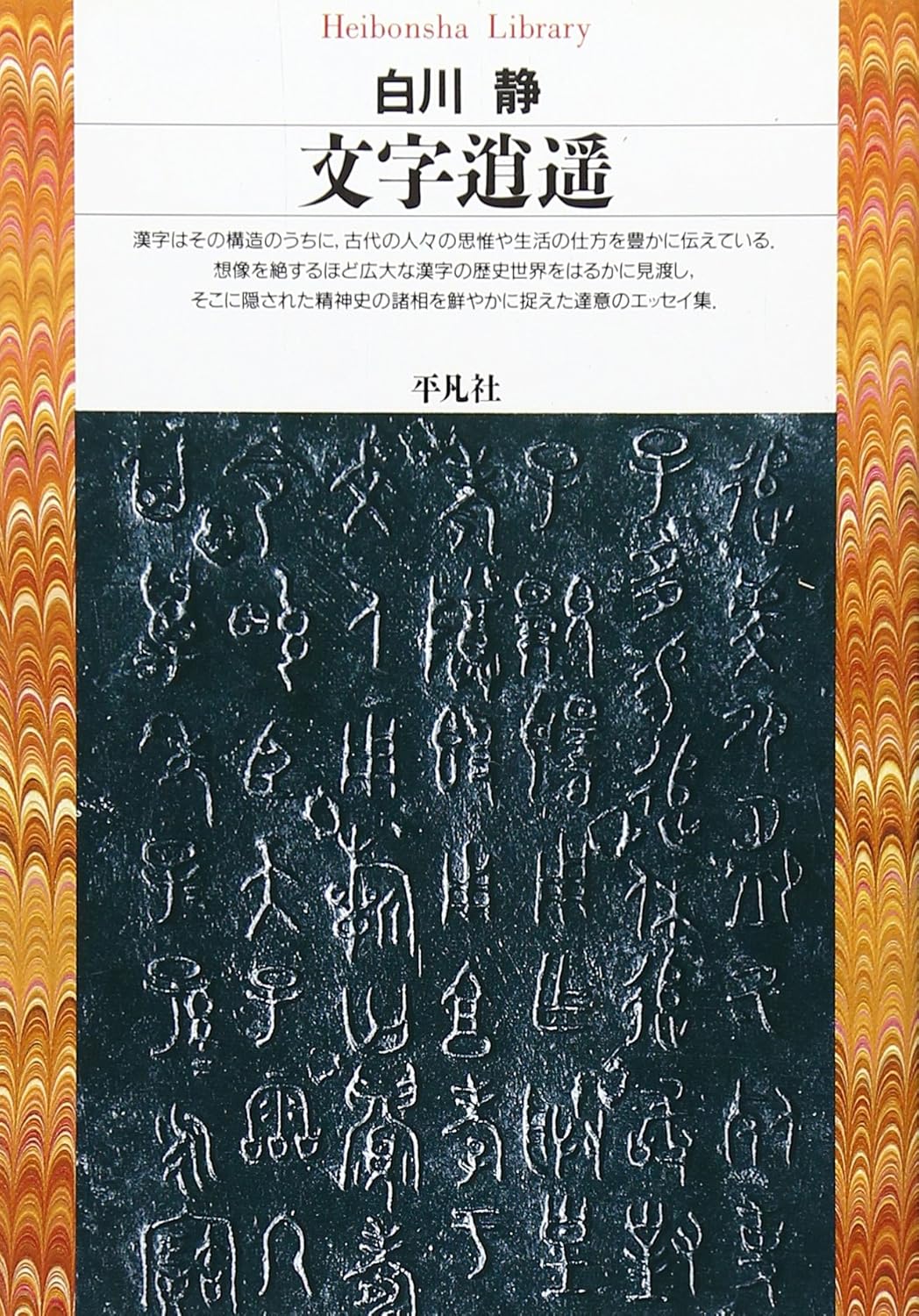想像を絶するほど広大な漢字の歴史世界をはるかに見渡し、そこに隠された精神史の諸相を鮮やかに捉えた達意のエッセイ集。
「字遊びは、かつては神聖な神の、自己顕現の方法であった。いまや神と人とは、その位置をかえている…」。白川漢字学への入門としての好箇の一篇である「遊字論」ほかを収録した。
著者は立命館大学名誉教授。先日96才で逝去した。学歴は尋常小学校卒。働きながら夜間の教育課程を経て大学教授になった異色の経歴であるが、漢字研究の第一人者として評価されている。
白川 静先生には、本当に感謝のほかない。
先生に巡り会えて、例えば、真という字にかような意味があるとは、といったことを考えるようになった。
白川先生によると、真という字は、行き倒れの死人を本来表していると。
さいしょに読んだ時の衝撃を忘れられない。
なんで、真という字が行き倒れの死人かといえば、
「……真という字は人を倒(さかさまに)した形の字である。
たとえば行路で斃れた人などは、悪霊となる恐れがあるので、万葉集にも柿本人麻呂がそれを弔う長歌など作っている。
埋葬することを填という。
しかし古代の人は死というものをあまり、忌まなかった。それは新しい世界への加入であり、永遠の生への出発に他ならないと考えたからである。
それで真は、そういう生没を超えた死生観をいい、その体得者を真人と称した。
これを絶対的な精神の体得者を意味する語にまで高めたのは、いうまでもなく老荘の思想であった。」
白川先生の驚くべき講義はつづく。
「……後世には、旅立ちの儀礼として祖道、すなわち「馬のはなむけ」とよばれる出発式が行われる。
中国の古代には、遠行に車馬を用いた。
そして旅の安全を祈り、犠牲の犬をその車輪でひき殺して出発するのである。」
↑この部分。我が国にも今川義元の故事があるのを思い出した。
出典は忘れたが、今川義元が桶狭間の戦いに(京都に)進発する際、罪人の老女を軍の先頭に連れてきて犠牲として切り殺したと。これぞ、血祭り。
そういう血生臭い風習が戦国の日本にもまだ残っていたものだろう。
「未来のことば」というエッセイも忘れ難い。
「昭和のはじめごろであったと思う。ある夕刊紙上に、「緑の札」という、50年後の社会をかいた未来小説が連載されたことがある。
…この小説では、50年後の人物の会話は、すべてカタカナでかかれていた…」
↑この部分面白い。たとえば韓国人というものは「すべてカタカナ」で生活してるようなものである。
韓国がノーベル賞を取れない理由はこれ ↓
■語源への手掛かりを失うハングル @@使えば使うほどバカになる劣等言語ハングル
▲韓国語では、化学元素H(hydrogen)のことを「suso」という。
これは漢字で書けば、「水素」で、日本人が作った和製の漢語なのだが、
私の受けた学校教育の場では、化学用語として、とにかく「スソ」というのだと教えられただけで、それは漢字で「水素」と書くのだとは、教えられていない。
だから、「スソ」は日常世界とは何ら関係する事のない純学術用語以外のものではなくなる。
▲現在の韓国のように、漢字を排除して殆どハングルだけを使っていると、
言葉に漢語や日本語のイメージは全く浮かぶ事が無く、語源の手掛かりも失うため、
全てが固有語であるかのような錯覚が生じてしまう。
▲しかし、日本語では「水素(スイソ)」という単語を教われば、誰の頭にも「みずのもと・水の素」という訓が浮かんでくる。
そのように純粋な化学用語でも、日常的な和語の世界に抵抗なくはいる事が出来る。
そのため日本では、韓国やラテン語から引用する欧米のように、学術用語が専門的な教育を受けたものにしか解らない、日常世界から遊離した言葉になる事も、それほど多くはないのである。
日本的精神の可能性、呉善花より http://toron.pepper.jp/jp/syndrome/jpnhan/youchika.html
2014/10/14 東亜【朝鮮日報/コラム】追い越せる日本、追い越せない日本…ノーベル賞受賞歴に見る韓国と日本の距離[10/12]
2014/10/16【韓国】 なぜ日本はノーベル賞を受賞できてわが国はできないのか
漢字のみの中国言語は致命的な欠陥言語だ
中国はすべて漢字表記だから、覚える漢字が多すぎてそっちに時間を大量にとられて学問にまわす時間がない。
要するに大量な漢字を単に覚えさせるだけに子供の成長が費やされ、会話の発達が遅れ
高度理論の展開など更々不可能にしてしまうのだ。
無駄に大量な漢字を覚えさせることで多くの脳の記憶領域を費やしてしまい、一番重要な創造的な超高度理論を発展する頭脳領域の余裕などなくなるのだ。
この致命的な欠陥を見事に解決したのが日本語である。日本人が開発した「ひらがな」は、劣った中国語の致命的な欠陥を完全に解決したのである
併せて読みたい
漢字百話 (中公新書 500) 1978/白川 静 (著)
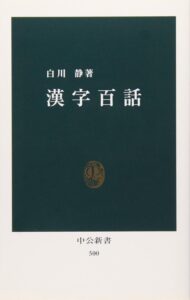
漢字: 生い立ちとその背景 (岩波新書) 1970/白川 静 (著)
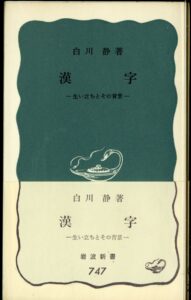
街道を行く 5つ星のうち5.0 漢字の神秘。 2014年7月6日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
何の遠慮もなく、有難味も感じないまま使い続けている漢字。
一体いつ頃誰が作ったものなのでしょうか。
それを探ってゆくことは、漢字がもつ神話のような物語を辿ってゆくことになります。
これは凄い知的で、想像力を試される道でした。
この本で白川さんが伝えようとしたことの百分の一位しか理解できてないでしょう。
正直、かなり難解な内容であったと申し上げざるを得ません。
しかし、漢字のもつ神秘的な世界に触れられるのが何とも言えない快楽のような感情が薄らと滲んでくるのです。
深い森の奥に見つけたきれいな水に手をつけたような。
人が神と共にあり、神と共に生きていた時代に神の意志を示すのに生まれたのが漢字です。
日本では至る所に神社を見つけることができますが、もしかするとそれこそ神と共に生きてきた証拠ではないでしょうか。
普段の生活の質を少し持ち上げてくれる素晴らしい本です。
17人のお客様がこれが役に立ったと考えています
呪の思想 (平凡社ライブラリー) 2011/白川 静 (著), 梅原 猛 (著)

3300年前に生れた漢字は、人が神の力を持つための手段だった! 白川静をこよなく敬愛する梅原猛が原初の文字に封じこめられた古代人の心について聞く、東洋の精神にせまる巨人対談。
孔子伝 (中公文庫BIBLIO) 文庫 2003/1/1白川 静 (著)
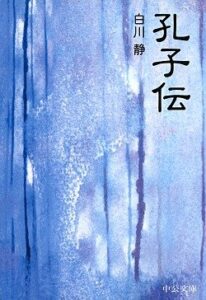
白川静先生はすべて読んでるが、もっとも衝撃的だったのはこれ。
孔子は、巫女の庶世子であった。
いわば神の申し子である。
父の名も知らず、その墓所など知る由もない。
儒はおそらく、もと雨乞いに犠牲とされる巫祝をいう語あったと思われる。
その語がのちには一般化されて、巫祝中の特定者を儒とよんだのであろう。
漢字とは何か 〔日本とモンゴルから見る〕 2021/7/27岡田 英弘 (著), 宮脇 淳子 (編集), 樋口 康一 (解説)藤原書店 日本文明の素晴らしさよ、日本人に生まれたこの「偶然」に感謝する…

日本の感性が世界を変える (新潮選書) 2014/鈴木 孝夫 (著) 漢字の読み方に日本式の訓読みがあることが日本語を救った…