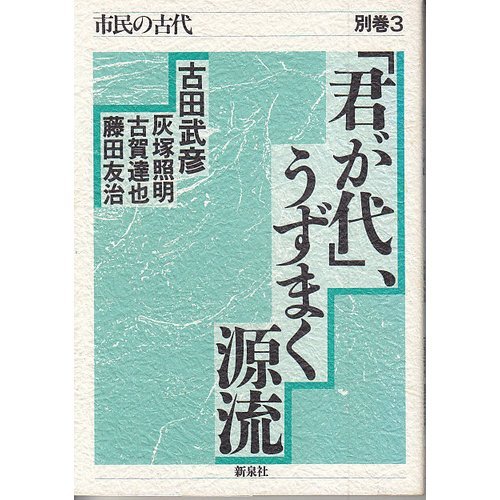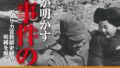さいきん、「君が代」に嵌っている。
国歌としての君が代ではなく、あの歌詞が出てくる君が代の、発祥まで遡ってみようということである。
珍しくこの話題ウィキペディアが充実してる。いくら何でも無視しきれないということか(笑)
君が代に関する諸説
「九州王朝」起源説による解釈 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%9B%E3%81%8C%E4%BB%A3
九州王朝説を唱えた古田武彦は自ら邪馬壹国の領域と推定している糸島半島や近隣の博多湾一帯のフィールド調査から次のような「事実」を指摘している[59][60]。
「君が代」は、金印(漢委奴国王印)が発見された福岡県・志賀島にある志賀海神社において、神功皇后の三韓出兵の際、志賀海神社の社伝によると、その食前において山誉の神事を奉仕したことにより、神功皇后よりこの神事を「志賀島に打ち寄せる波が絶えるまで伝えよ」[61] と庇護され
今に伝承されている4月と11月の祭礼(山誉め祭[62][63])にて以下のような神楽歌として古くから伝わっている。
なお、この山誉め祭は、民俗学的に価値のある神事として、福岡県の県指定の有形民俗文化財[64] に指定されている。
君が代は 千代に八千代に さざれいしの いわおとなりてこけのむすまで
あれはや あれこそは 我君のみふねかや うつろうがせ身み骸がいに命いのち 千せん歳ざいという
古田 武彦先生を筆頭に「君が代」は九州王朝の歌ではないかという考察の数々である。
なかでも、この本の、古賀 達也氏の考察が凄い。
「君が代」によく似た歌 43ページ
しかし、万葉集編纂時にすでに「君が代」が歌われていたことを証明する方法はないものだろうか。
この点、実は「万葉集」には「君が代」と関係がありそうだとされている興味深い歌が一首だけある。
万葉集第2巻の「和銅4年歳次辛亥、河辺宮人、姫島の松原に嬢子の屍を見て悲しび作る歌2首」がそうだ。
妹が名は 千代に流れむ 姫島の 小松が末に こけむすまでに
明らかに「君が代」と同じモチーフで詠まれた歌だ。岩波の「日本古典文学大系」の解説では、作者の河辺宮人を伝未詳としており、姫島も摂津のどこかであろうとしている。
言わば、取り扱いに苦慮しているのだ。
しかし、糸島半島や博多湾岸の人間には、この歌の情景がはっきりと見える。糸島半島の沖に浮かぶ姫島、そしてコケムスメ神を祭る船越から糸島水道を抜けて博多湾岸の千代の松原に流れる海流。このリアルな臨場感。
この歌も糸島や博多湾岸でこそ理解できる、当地の歌だったのだ。
それだけではない。「この歌は当地の歌に間違いありません。私の現役時代、糸島で溺れた人の遺体が博多湾岸の志賀島に流れ着いたことがよくありました」
灰塚氏は地元警察のOBであり、こうした捜査に関わられた経験をお持ちとのこと。
「小松が末も地名ですよ。コケムスメ神がある船越から糸島水道の南対岸に、松末(現地音ではマツエとのこと)がありますが、現地には小松末もあります」
志摩郡「河辺の里」
とすれば、作者の河辺宮人とは何者だろうか?
10世紀に成立した、わが国最初の分類体系百科事典「和名類聚抄」に記された、志摩郡の7つの郷のうちに「川辺」があったのだ。
ここでいう志摩郡とは今の糸島郡の半島部分にあたるが、問題の川辺郷は現在では川辺の地名は残っていない。
(和名抄) 志摩郡は、 鶏永・志摩・久米・川辺・明敷・韓良・登志 の7部。
!!!
↑これは驚くべき証言ではないだろうか??
考古学者・森浩一氏が、九州からいくら鉄が出てきても畿内説の考古学者は
無視するが、近畿地方から鉄のかけらでも出てくれば大騒ぎする、
と言っていたが、これは畿内説の考古学のあらゆる面で妥当する。
九州の数百と言われる高度な鉄鍛冶遺跡には触れず、淡路島の原始的な
鉄鍛冶遺跡を「日本最大級」と発表したりする。
畿内説の考古学は少し疑ってかかる方がいい。
淡路島 五斗長垣内遺跡
遺物の鉄器は、矢尻、鉄片、鏨(たがね)、切断された鉄細片など75点が出土した。
熊本 西弥護免遺跡
西弥護免遺跡では弥生終末期 581点の鉄器が出土している。さらに鉄滓などもあり。
↑ 75 対 581 !! まるっきり比較にならない…
しかも、狗奴国と思われる熊本県には、弥生時代の鉄鍛冶遺跡がほかにもゴロゴロある。
二子塚遺跡(熊本県上益城郡嘉島町) およそ、1000点を超える鉄片が出土。
狩尾遺跡群(熊本県阿蘇郡阿蘇町 狩尾)
狩尾・方無田遺跡
狩尾・前田遺跡
池田・古薗遺跡
方保田東原遺跡
↑まだまだあるが、このあたりでやめておく。ただ、感慨深いのは、熊本県の弥生時代の鉄鍛冶遺跡をまとめて抽出したのが広島大学の川越哲志という人で、それは非売品で外部に伝わっていなく、邪馬台国九州説の何人かが分かりやすくまとめたものらしい。2010年の時点で。
邪馬台国畿内説の人がよく言うことに、「あの田舎の九州」に7万戸はおかしいというもの…
しかし、我が国でもっとも早い時期の延喜式を見た方がいい。
【稲作の分布】古代は九州のほうが圧倒的に大きい。ほぼ、3倍!!!
旧国 『延喜式』出挙稲数(束)
◆畿内 2,087,126
山城 424,070大和 554,600河内 400,954和泉 227,500摂津 480,000
◆西海道 5,990,581
筑前 790,063筑後 623,581豊前 609,828豊後 743,842肥前 692,589肥後 1,579,117
延喜式は10世紀だから、古代3世紀ごろはもっと差が大きいんじゃない
弥生時代の農業生産はおそらく畿内全域と九州で10倍くらいは差があったでしょう。
延喜式 出挙稲数
畿内 2,087,126
山城 424,070
大和 554,600
河内 400,954
和泉 227,500
摂津 480,000
西海道 5,990,581
筑前 790,063
筑後 623,581
豊前 609,828
豊後 743,842
肥前 692,589
肥後 1,579,117
日向 373,101
大隅 242,040
薩摩 242,500
壱岐 90,000
対馬 3920
日本の真の歴史について無知な心理学者の岸田秀は言う。
「わたしによれば、日本人が天孫降臨神話を作り出したのは、すでにあちこちで繰り返し述べているように、7世紀に白村江の戦において、日本の水軍が唐・新羅の連合軍に惨敗して朝鮮半島から追い出された敗北感と屈辱感を補償するためというか、ごまかすためである」嘘だらけのヨーロッパ製世界史 2007/岸田 秀 (著)新書館より
白村江の戦いで、唐と新羅の連合軍と戦ったのは九州王朝の兵隊である。
畿内ヤマト政権は関係していない。
万葉集に白村江の戦いの歌がひとつもない!
畿内ヤマト政権がまとめた万葉集は「7世紀~8世紀」にまたがる歌集であり、その時期の最大の事件は白村江の戦いである。
だが、万葉集全20巻中、「白村江の戦い」を歌った兵士やその恋人、家族の歌が一切収録されていない。
畿内ヤマト王権に水軍がない。これまで、遺跡もまったく見つかっていない。
天孫降臨神話を作り出したのは、藤原不比等が、天皇というものを強化して(作り出して?)、自分たちがその天皇に嫁さんを差し出して、恒久的に食い物にするために生み出した「システム」だからである。(上山春平「神々の体系」中公新書)
これは明らかに岸田秀の無知による「唯幻論」の暴走だろう。
何でもかんでも心理学上の「補償」概念を当てはめるという無理を犯している。