何をもって幸福とするのかという難問があるが、私が今まで読んできた中で最良の「幸福入門書」だと言えるかもしれない。
根底に老荘思想がある。
全部すごいが、いちばん私が感銘を受けたのは、中での「分福論」である。
誰しも一度は、この時は何をやっても好調だった、競輪でツキまくり、ボートレースで勝ちまくり、競馬で当たりまくり、といった時期があるものである。
そんな時には、福を敢えて他人に分け与えることが大切であると著者はいう。
翠 5つ星のうち5.0 面白い!! 2015年12月15日に日本でレビュー済み
とても為になる本です。
『難しい』というだけで低評価をつけてる人がいますが、『難しい』という理由により本の評価を下げるのはおかしいです。
そもそも読めてないのだから評価など出来ないはずです。
自身の読解力不足を本のせいにしてはいけないと思います。少なくとも、この本をきちんと読んでいればそのような評価はしないでしょう。
なぜなら、『成功者は自分の力として解釈するが、失敗者は周囲や運命の力として解釈するのである』と本書にも書かれているからです。
人のせいにしてしまうとそれまでであるが、自分のせいであれば、自分の事なのだから幾らでも直せる。それにより運命が変わるということなどが書かれています。
難しい漢字なども多く使用されていますが、内容自体は実例などが挙げられておりました。
この本を読んだ充実感は嬉しいです。
時代背景が異なるので解釈が困難な箇所もありますが、気付かされるものがある本でした。
超訳 努力論 (ディスカヴァークラシックシリーズ) 2013/11/29 幸田 露伴 (著), 三輪 裕範 (編集, 翻訳)

『五重塔』「風流仏』といった小説で有名な、明治・大正・昭和を生きた大文豪・幸田露伴だが、
明治末に書いた人生論である『努力論』は当時から現在まで、多くの人に愛読されてきた。
本書は、自らも数え切れないほど読み返し励まされてきたという編訳者が、 『努力論』の最も重要な箇所を選び出し、
現代では馴染みが薄くなった言葉や表現を思い切って超訳、 読みやすくわかりやすい形でお届けする。
↑私も、渡辺昇一先生も、読んだ方の感想として、明治時代に書かれたものであり、その上、幸田 露伴は老荘思想を極めた人物なので、極めて読みづらいという評が多い。そんな方はご安心を、こういう本がある。これから始めて本体のほうを読んでみるというのもいいかもしれない。
今は亡き、渡辺昇一先生もこの本が大好きだったらしく、解説書を書かれている。併せて読んでいただきたい。
「幸田露伴に学ぶ『努力論』」 CD – 2021/7/7 渡部昇一 (著)
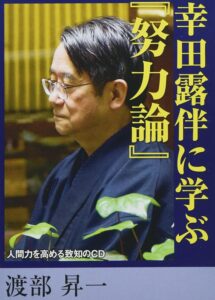
・平清盛、源頼朝、徳川家康に見る「惜福の精神」
・国家にこそ求められる「惜福の精神」
・ノモンハン事件の実情が示す兵隊の力に頼りすぎた日本の問題点
・勤勉誠実な日本人が積み上げたものをいとも簡単に投げ出すエリートたち
・豊臣秀吉、石田三成が家臣に対して発揮した「分福の精神」
・戦後の日本で根こそぎ奪われた「植福の精神」
【収録時間107分/CD2枚組】
世界初ChatGPT-4連携AIボイスレコーダー PLAUD NOTE
![]()
幸田露伴の語録に学ぶ自己修養法 2011/渡部 昇一 (著) 致知出版社
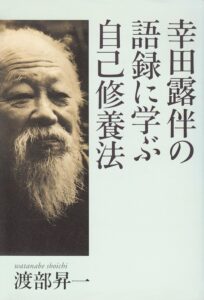
幸田露伴の「幸福論」から渡部昇一氏が選んで自らの体験、考察を述べている。
「惜福、分福、殖福」の説明とその大切さから書き出しは始まる。
第一回文化勲章受章者であり、代表作『五重塔』で知られる作家・幸田露伴(1867~1947)。
かつて慶大塾長小泉信三博士に「百年に一度の頭脳」と言わしめた露伴の実績は、現在、全42巻の『幸田露伴全集』として結実している。
その昔、若き露伴は電信技師として北海道へ赴任する。
しかし、文学への思いを断ち難く帰京を決意。
連絡船で青森へ渡った後、徒歩にて帰京をするが餓死寸前にまで至る。
その間の野宿で、露を伴って寝たので「露伴」と名乗った。
所謂出世コースとは無縁だった露伴は、その人生航路において、自己修養の重要性を認識し実践していたのである。
本書は、当代随一の論客として活躍を続ける渡部氏が、露伴の思想と実践とに、自らの実体験を重ね合わせて綴った、すべての現代人に贈る自己修養論である。
本書で取り上げている作品は、『努力論』『修省論』『靄護精舎雑筆』の3作。
渡部氏はこれらの作品を文字通り座右に置き、数え切れないほど読み返してきたというが、そのいずれにも、露伴独特の味わいのある文章中に、万人に共通する人生の機微、生き方の極意が述べられている。
そして、それらは今日のような時代状況の中では、前途に立ちはだかる困難を、自らの手で切り開かんとする人たちの心を奮い立たせ、充実した気を注入するものとして大いに役立つに違いない。
露伴の「生き方の原理原則の言葉」に心底から共鳴し、露伴を敬愛してやまぬ渡部氏の手になる本書には、明治から昭和の文壇の巨匠、そして現代の碩学が実践してきた自己修養法、生き方のエッセンスがぎっしりと詰まっている。
jinchoku 5つ星のうち5.0 自助精神のエッセンス
2003年5月9日に日本でレビュー済み
現代は経済のグローバル化で適者生存の原理がより鮮明になっている。
渡部昇一氏は、こうした時代にこそ「修養」が重要だと述べる。
なぜなら、修養とは自助努力を尊ぶ思想だからだ。
幸田露伴は修養を体現した人物だ。
学歴はないが、文筆により文化勲章を受け、時の慶應義塾塾長、小泉信三をして「百年に一度の頭脳」と言わしめた。
その露伴の代表作『努力論』『修省論』『靄護精舎雑筆(あいごしょうじゃざっぴつ)』から学ぶ意義は大きい。
本書では自己実現を果たす物の見方・考え方、富を育てる方法といった自助精神のエッセンスが紹介されている。
難読な露伴の原文も渡部氏の豊富な事例を引いた巧みな話術によって読みやすく仕上がっている。
「社会はすべて数から成り立っている」ピタゴラス 数霊―数が決める運命 昭40 金子 彰生 (著) オリオン社
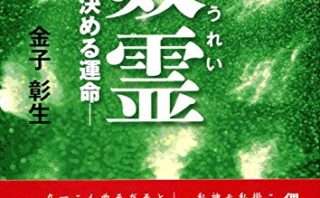
この本を取り上げたらコメント欄から、この本を古本屋で買い、読んでみたら、計算方法が難しすぎるという問いかけがあった。
著者、金子 彰生氏は明治34年(1901)1月26日東京日本橋に生まれる。
大正15年(1926)1月16日、箱根登山電車脱線転落のさい乗り合わせて遭難、多数の死者の中でただ一人の無事生存者となる。
その後「生と死」に深く興味を覚え、山田耕筰先生の『生まれ月の神秘』を読みますます興味を覚える。以後、数に憑かれたように、数の神秘に取り組み、数の権化となり研究に没頭し、「数と運命の研究」のまとめに専念する。
死者17名の大事故でただひとり、ほとんど無傷で助かったのがこの本の著者である。
著者が特異なのは、たったひとり生き残ったことの理由を27年間も追求したというところだろう。世界で今もどこかで事故は起きてるだろうが、その原因を外部的要因以外で探そうとする人はいないだろう。
↑この人のことはもっともっと知られてよいと、取り上げたのだが、この人は、人の幸福は、時期である、と言い切っている。
死者17名の大事故でただひとり、ほとんど無傷で助かったのは、時期が良かったからだと言い切っている。
計算の仕方が面倒だし、この本を読んでなるほど実人生に応用するとなると難しいだろう。
たとえば1年間を生きてみて、この月はついてる、この時期は行けてると感じられる月がどんな人にもあるものである。
その好調だった月を覚えていたらどうだろうか。
例えば、その人は2月と6月に良いことが集中的にあったなら、翌年も、2月と6月に新しいことを始めてみるとか、この月に大きな事業を始めてみようかなとか、なにも大きなことでなくとも旅行でもいい。
まさしく、死者17名の大事故でただひとり、ほとんど無傷で助かったのがこの本の著者・金子 彰生氏だから、時期というのは大切である。
自分が助かったのは、ただただ時期が良かっただけだと金子 彰生氏が言い切っているのだから。


