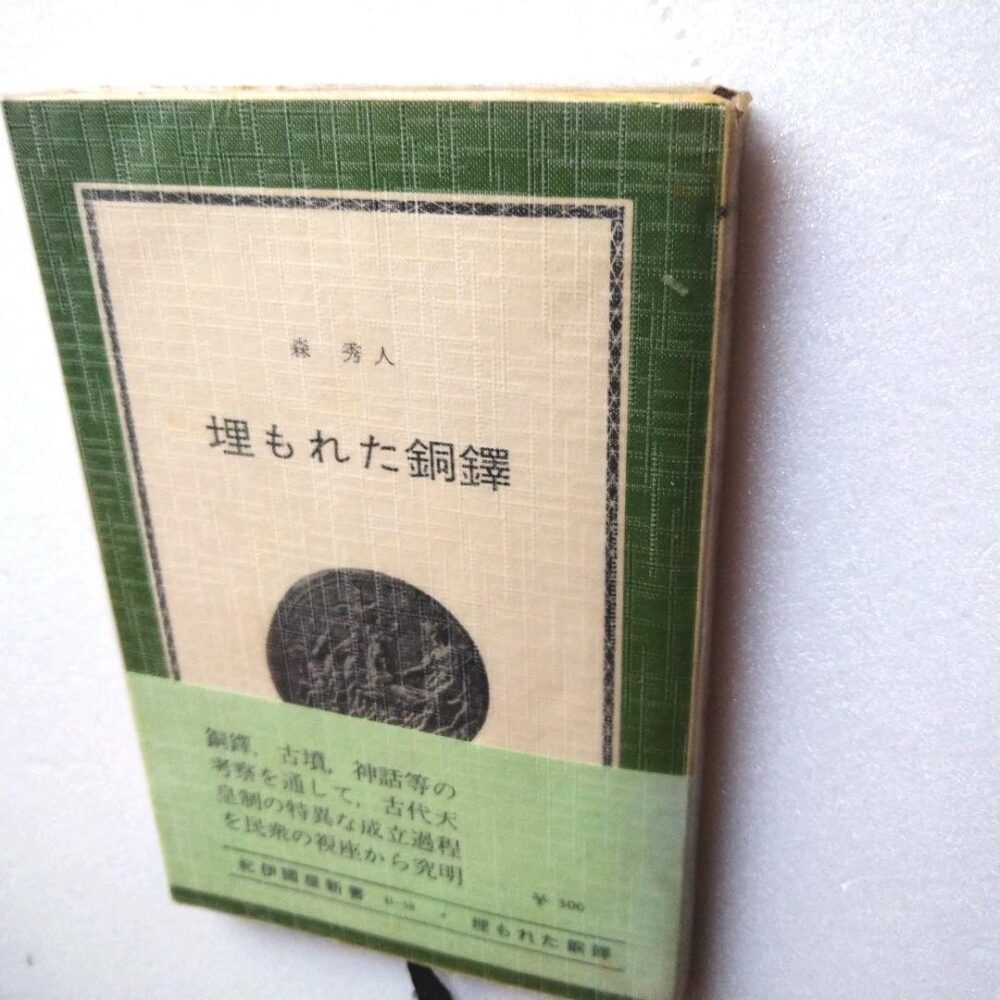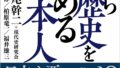本書は、1970年出版だから、実に55年前の本である。
さる古本市で20年前見つけて購入したものである。
以来、古本屋、古本市、数々めぐっているが以来、一度も見かけない本である。
著者は「思想の科学」の元・編集長、他に釣りのエッセイなどたくさん書いて、惜しくも数年前に亡くなってる。
だが、ほとんど忘れられたこの著者のこの2冊は凄い。
著者は日本古代史に関しては、この2冊しか書いていないが、信州が生んだ考古学者である藤森栄一氏とも深い付き合いがあり、こと知識にかけては大学の考古学者に引けを取るものではない。
藤森栄一という信州に根を下ろし古本屋と旅館を経営しながら、日本の考古学に多大な貢献をした人物がいた。
古代史論争―日本の青銅器文化 (朝日選書) 1982/森秀人 (著)
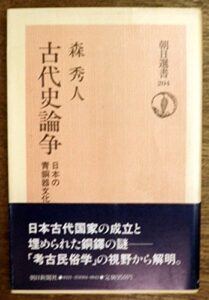
2, 古墳のシンボル 35ページ
のべ140万人の労力を費やしたと伝えられる仁徳天皇陵は仁徳の生存中から建設されていたという。
すると西暦で言えば、400年ごろの話である。仁徳天皇陵は古墳中最大であるから、古墳時代の中心をここに置くのことは正しい。どのような文化も、中心において最高となる。
少なくとも墳墓の形式から考えた場合、畿内から古墳文化、いわゆる陵墓(みささぎ)が生誕したということは否定される。
畿内には、古墳文化を作り出しうるような先・プレ古墳文化はなかったし、小古墳文化もなかった。
畿内だけではなく、銅鐸出土地全般にわたって、この地の人々は働くことに熱意は持っていても、墳墓を作ることに少しも関心を持たなかった。

野洲市歴史民俗博物館(銅鐸博物館) | 滋賀県博物館協議会
小林行雄の「古墳の話」は、考古学では稀なほどのベストセラーであるが、前期のごとき古墳をめぐる話をなぜか避けている。
同書203ページは、考古学の著述のなかではもっとも詭弁に満ちた文章で成立しているが、
それはまず、畿内にはそうした古墳を作り出す先古墳文化がなく、それは北九州にのみ存在するという前提をたてながら、巧妙に、「古墳に先行する畿内の墓は、まだ人々の気付かないところに、ひそかに隠されているのだろう」という(仮説)を紹介しながら、
「そういう小規模な墓があったことを、しいて否定するわけではないが、古墳は小規模な墓から徐々に変化したものではなく、急に発生した要求によって、飛躍的に形成されたものだと考えるのである」
?????????????
言うまでもなく、小林行雄のこうした文章の詭弁は、苦しい言い逃れであり、学者として恥ずべき欺瞞である。
それでは、なぜこんな珍妙な(小林行雄の)伝世鏡説ができたのかといえば、
ヤマタイ国 畿内 自生論者の小林行雄にとっては、北九州の弥生墳墓からは前漢時代の古式の銅鏡がたくさん出るのに、
畿内のそれから出てこないことは、畿内文化が鏡と縁がなくなってしまうからであり、そのために畿内の弥生人だけは、銅鏡を尊重するあまり伝世し、子孫に伝えたと主張したのである。
↑邪馬台国畿内説の根幹ともいえる小林行雄氏の説が、いかに詭弁に満ち満ちたものであるか明白であろう。こういう森秀人氏のような、まっとうな論がかき消されている !!

日本最大の銅鐸、9年ぶりに里帰り 安土城考古博物館で展示:中日新聞Web
YouTubeには色々と不満がある(特にちょうせんじん関係のコメント削除)がこういうものを無料で見られるというのは感謝感謝だ……畿内ではありえぬ「邪馬台国」 — 考古学から見た邪馬台国大和説 関川尚功
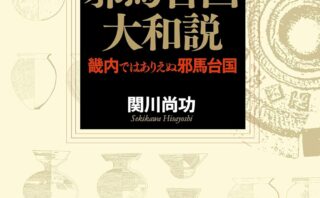
考古学者、歴史学者は、祭りごとのために築かれたと言ってるが、たった400年(古墳時代)に、20万基もだよ、冗談は顔だけにしてくれと言いたくなるではないか。
今に比べれば、はるかに食料も乏しい、人口も少ない中での20万基だよ。
「ピラミッドの目的は完成後の『用途』にあるのではなく、造るという『製作』過程そのものにあるのである」
『ピラミッドの謎』1975 物理学者・クルト・メンデルスゾーン
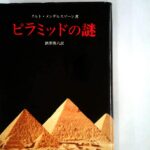
物理学者、メンデルスゾーンの知見(ピラミッド公共事業説)は我が国でおびただしく造られた古墳にもそのまま当てはまる。
消失した(宅地化、農地化)されたものを含めれば20万基以上の古墳がこの狭い日本列島に造られたものと思われる。
まずこれを異常と思わずしては先には進まない。
![]()
土偶を読む――130年間解かれなかった縄文神話の謎 2021竹倉 史人 (著) 晶文社
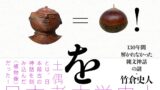
人類学者・中沢新一 372ページ
「日本のなかでは、考古学が、茶道や華道のような家元制度とよく似た発展をしているなと思いますね。
ひとつひとつの所作にものすごく重大な意味を持たせて分類されていくんだけども、それは閉じられた世界のなかだけで意味を持つことで…」
↑すごく共感する。現状の日本考古学に対する至言ではないか。
邪馬台国畿内説なんか、完全に家元制度だ。
>これに対して、この数年間に調査のおこなわれてきた大和古墳群での中山大塚、下池山、黒塚などの前期古墳の埋葬はいずれも木棺を壮大な竪穴式石室で囲みこんでいたし、若い日の僕が発掘に加わった櫛山古墳は石棺を竪穴式石室のおさめていた。
今回発掘されたホケノ山古墳では、木棺の外側に木槨と石室との2重の外部施設を備えていて、倭人伝が記している倭人の葬法には合っていない。森浩一「関東学をひらく」より 2001 朝日新聞
「魏志倭人伝」には、倭人の葬式は、 棺あって槨なし。」 と、明記しているのだ。
木槨のなかに木棺があったのでは、「魏志倭人伝」の記述に合っていない。<
ではなぜ、「はじめに邪馬台国畿内説」なのか。
それはそのように教育されたからである。京都大学を中心として、その伝統にもとずき、考古学の分野で、そのような徒弟制度ができあがっているからである
その徒弟制度(いや、家元制度かな 笑))からはずれれば、就職も生活も出世も不利となる可能性がある。
こんな連中(邪馬台国畿内説派)に税金を使うのは無駄である。
九州王朝論者(法隆寺移築説)からみた、「古墳はなぜつくられたのか?」

古墳はなぜつくられたのか??
これに対する答えは、3点セットで考えなくてはいけないとつくづく思う。
①高地性集落 → ②古墳造営 → ③決まって、被差別部落が存在する。
九州王朝論信奉者からみた「前方後円墳」 (歴史文化ライブラリー 616) 2025/2/26 下垣 仁志 (著)吉川弘文館 前方後円墳は墓ではない、墓も初期にはあったが…
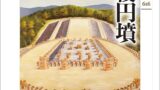
@香川県善通寺市・旧練兵場遺跡 九州地方からの移住者住居跡 九州地方からの移住者の存在を県内で初めて確認した。同遺跡は、弥生時代中期から古墳時代にかけての竪穴住居跡が多数発見されている県内最大規模の集落遺跡。
@紫雲出山遺跡(しうでやまいせき)は、香川県三豊市詫間町に所在する弥生時代中期後半の高地性集落遺跡
↑直線距離で8キロくらいだから、いい感じじゃね? 時代もぴったり合う
香川県善通寺市・旧練兵場遺跡に九州勢力が橋頭堡を築き、紫雲出山遺跡に籠もった原住系・銅鐸民との血みどろの戦いが行われていた証拠だよ
香川県には7年前、古墳を見るために東京から自転車で行ったことがある。
その時には気がつかなかったポイント…
この紫雲出山近辺は、被差別部落が多いところだと、「福田村事件」のことを書いてて知った。
じつに1600年前の原住系と、攻め込んできた新興の神武天皇派の対立がそのまま1600年余りも持ち越されてきた地域だ。間違いない。
この狭い日本列島に20万基も古墳が作られた理由もそれ…
高地性集落と倭国大乱―小野忠熈博士退官記念論集 1984/雄山閣「高地性集落」を追いかけて…

とにもかくにも、畿内説はすでに破綻しているのではないか。
三角縁神獣鏡が現在まで600枚以上も出土している。
小林行雄が分配説で畿内説を補強して一世を風靡したが卑弥呼が100枚しかもらってないのに(笑)、すでに600枚(700枚を超える説もある。正式な手続きを踏まず古物商などに流れたものを含めれば優に1000枚は超えていよう)とはおかしいではないか。
三角縁神獣鏡はまちがいなく国産だよ。
世の大学の歴史学者たちはそれでも頑なに畿内説支持というのだから恐ろしい。
税金の無駄遣いではないのか。
銅鐸文化の消滅をこじつけでしか説明できない時点で邪馬台国畿内説はダメ。
巨大古墳は、先住民(銅鐸民)の反抗を封じるために作られた無益なモニュメント。
結果ではなく過程(強制労働)に意味があった。
土器の編年とか、ほんとにくだらない。
支配者(勝った側の)の心を知ること。