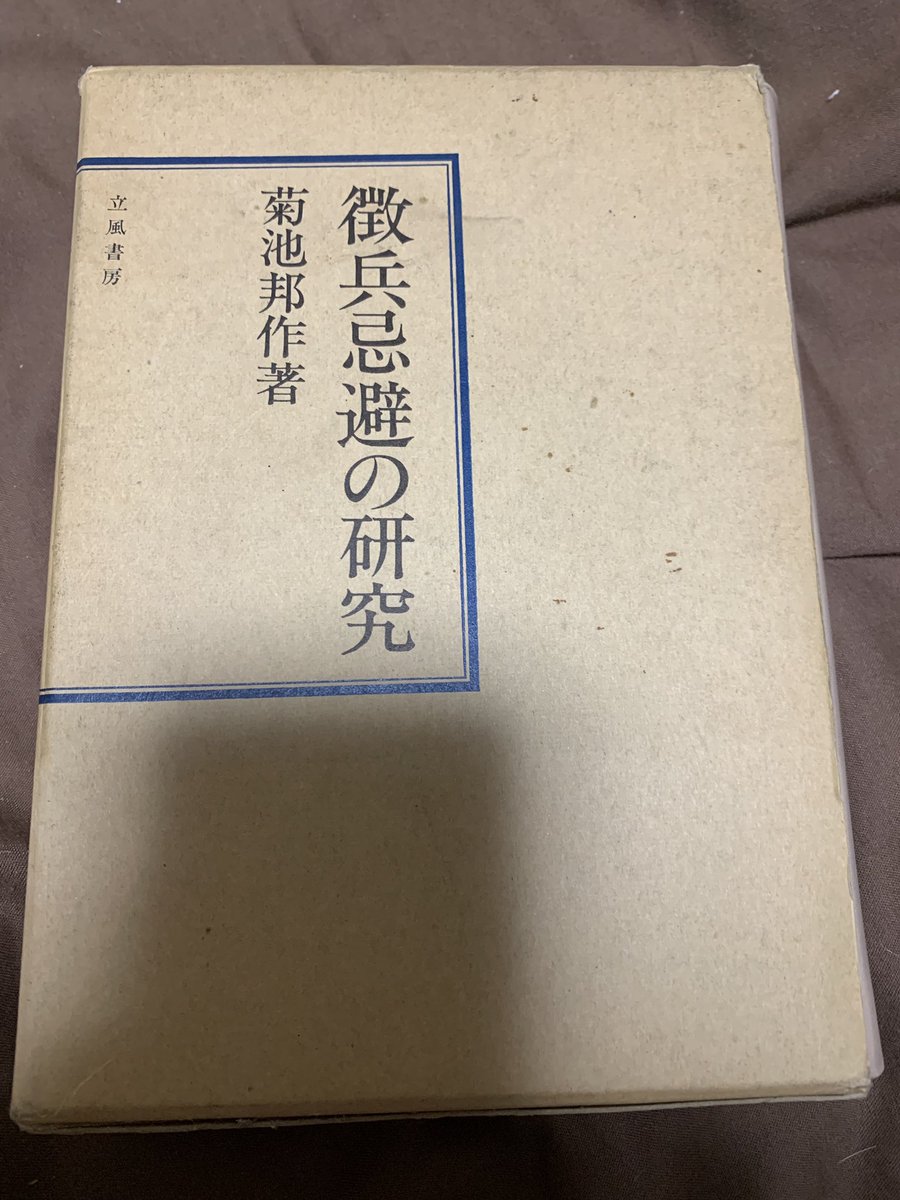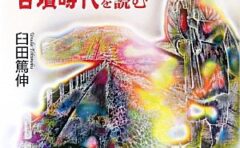私にとって、徴兵忌避といえば、「笹まくら」をおいてほかにはない。
笹まくら (新潮文庫) 1974/丸谷 才一 (著)
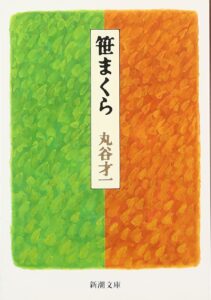
笹まくら…旅寝…かさかさする音が不安な感じ…やりきれない不安な旅。
戦争中、徴兵を忌避して日本全国に逃避の旅をつづけた杉浦健次こと浜田庄吉。
20年後、大学職員として学内政治の波動のまにまに浮き沈みする彼。
過去と現在を自在に往きかう変化に富む筆致を駆使して、徴兵忌避者のスリリングな内面と、現在の日常に投じるその影をみごとに描いて、戦争と戦後の意味を問う秀作。
日本文学史上、安部公房の「砂の女」と並ぶ最高傑作と信じてる。
徴兵忌避者のスリリングな内面と、現在の日常に投じるその影をみごとに描いて、戦争と戦後の意味を問う秀作。
抜群の着想、あの孤絶、あの哀感、あのスリル、すべてにおいて優れた小説である。
ところで、この傑作小説が夏目漱石の徴兵拒否の事実がもとになっていることに触れている類書が余りにも少ない。
丸谷才一氏の著書、「徴兵忌避者としての夏目漱石」(丸谷才一全集 第9巻所収)で、そのことについて書いている。
北海道に住所を移していたのも 徴兵拒否のためだとか 言われている。
小説「こころ」の主人公が自殺するのは、徴兵逃れをしたことに対する漱石の良心の呵責が表現されたものだという説がある。
まず初めに、「徴兵忌避者としての夏目漱石」という事実があって、丸谷才一の脳裏に深く沈潜し、やがてそれが大傑作・笹まくらに結実したんだなというところがわかって興味深い。
夏目漱石… 坊ちゃんと吾輩は猫である、は凄まじくおもしろかったが、それ以外がクソつまらないという感想。
この説の真偽はわからないが、たしかに戦前の作家には、徴兵という心配事が人生につきまとったのだ。
作家という観点で、いろいろ分析しているが本当のところは本人じゃなきゃわからない。
![]()
![]()
ところが、この「徴兵忌避の研究 (1977年) 菊池邦作」に言及がないのはどうしたわけであろうか。
巻末の参考文献にもないのだ。
類書がないと嘆いているのに、である。
不思議である。
笹まくらが、1974年に書かれ、徴兵忌避の研究が1977年に出てる。
3年もの間隔が空いているのに、徴兵忌避の研究の著者が笹まくらを知らないはずがない。
作者が気難しい?
その可能性はある。
なにせ、1899年、群馬県伊勢崎市生まれ。1931年、小林多喜二、村山知義(傑作、「忍びの者」の作者)らとともに検挙され、同署占拠事件のきっかけとなったというバリバリの筋金入りの共産党員である。
「笹まくら」の言及がないのは、置いておいて本書が興味深いのは間違いない。
「死亡診断書を偽造し戸籍を抹殺した山田多賀市の場合」
「逃亡して新しい戸籍を作った陸軍中尉」
「甲状腺剤(チレオリシン)を自分に注射して徴兵を逃げ切った医者の卵」
「狂人を装い徴兵を免れたある老人の手記」
いくつか、気になる箇所があった。
あとがきにある、明治維新の日本の徴兵制度を武士階級の専横、延長だと決めつけているところ。
帰農ということばを著者は知らない?
武士といっても、ずっとその人が武士だったわけでない。
大きな時代の変わり目には、不本意ながら、農民になって時代をやり過ごした人たちも多い。
逆もある。農民から武士へという流れ。
有名な話だが、勝海舟の先祖は新潟県出身の按摩師である。武士の株を買ってサムライになった。そういう人もいる。
明治維新の日本の徴兵制度が武士階級の延長なわけはない。